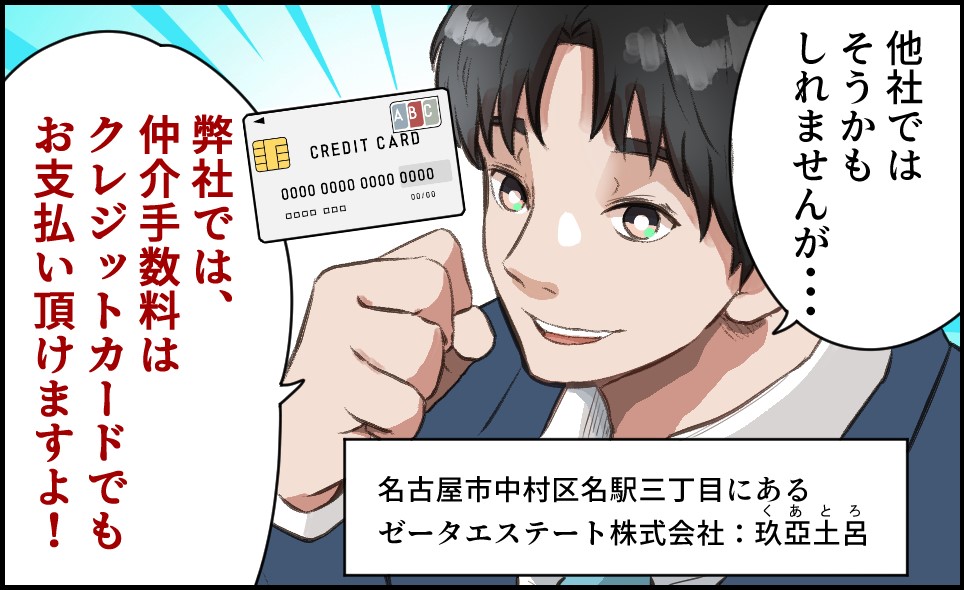不動産購入時の名義はお金を払う人の名義!追加は贈与税が課税?

不動産売買契約締結後、諸事情により不動産購入時の名義に買主様を追加する必要が出てきた場合や買主様を削除する必要が出てきた場合等いろいろあると思います。
本来はこういった買主様の追加や削除が無いように事前にしっかりと計画を練る必要がありますが、契約は購入申し込みから1週間以内が原則です。
名義はお金を支払う人の名義にする原則がありますので、しっかりと検証して名義をつける必要があります。
この記事では、不動産購入時の名義や名義の追加・削除について解説していきます。
Contents
不動産購入時の名義は重要
「不動産の考え方は日用品等の【物】と同じ」私は何人ものお客様にこう言ってきました。不動産は特別な物ではありません。
日用品と同じ【物】になりますが、高価な分、購入方法を現金以外でも考えて購入する物です。同じような物に車があります。車の例を出すと納得してくれることが多かったです。
日用品と不動産の違い

日用品と不動産の違いですが、何があるかと言うと
- 不動産には原則として名義をつける
- 名義はお金を支払った人のみ
- 共同(共有)で購入した場合支払ったお金の割合に応じて持ち分をつける
- お金を支払っていない人の名義をつけた場合持ち分に応じて贈与税がかかる可能性がある
- 上記は夫婦や親子でも免除はされない
- 所有していると固定資産税や都市計画税が課税される
- 上記を支払わないと差し押さえになる
- 善管注意義務(善良な管理者の注意義務)もあったりする
名義や税金って話になると自動車(車両運搬具)にも似ています。
【現金購入の場合】不動産購入時の名義予定の人が【増減】した場合で売買契約前の場合・売買契約後の場合
この場合は、売買契約の前日までには不動産業者へ連絡をしておきましょう。
不動産売買契約の前の場合

変更が売買契約書に反映されていますから契約当事者が署名(記名)・押印をして終わりです。
不動産売買契約の後の場合

不動産売買契約後に不動産購入時の名義予定の人が増減した場合は、「覚書」を取り交わして対応します。
売主様・買主様それぞれ覚書原本を保管してもらいます。この時に収入印紙200円を貼り忘れ無いようにご注意ください。
【住宅ローン利用の場合】不動産購入時の名義予定の人が【増加】した場合で売買契約前の場合・売買契約後の場合
よくある話しなので、遠慮なく不動産業者に相談してください。そして、相談する時は出来るだけ早めにしてください。
不動産業者が火曜日や水曜日の休みでも時と場合によっては遠慮なく電話した方が良いです。正直な話、その方がかえって良かったりもするものです。
経験談ですが、買主様が電話をためらって期日に間に合わなくて名義を変更できなかったってパターンもありました。
不動産購入時の名義予定の人が【増加】した場合で不動産売買契約の前の場合
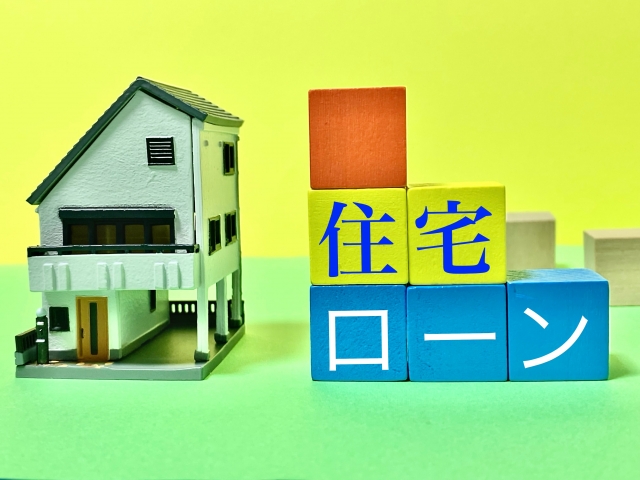
〇住宅ローンを利用するのであれば、少し手続きが煩雑になります。
銀行によって対応は様々だと思いますが、売買契約前ですが、住宅ローンの事前審査を行っているので、住宅ローンを利用する銀行へ名義人が増加する旨の連絡を入れ銀行の承認を受ける必要があります。
そして、銀行がそのまま売買契約書に追加買主の署名(記名)・押印をして、本申込で対応すると言えばその通りにすることで大丈夫です。
しかし、銀行が追加買主を入れた状態で事前審査をやり直すとの事になったら、追加買主がどんな位置(担保提供者・連帯債務・連帯保証等)になるかによって必要書類が変わってきます。その通りの書類を出来るだけ早く取りそろえる事が必要になってきます。
この判断は銀行の判断になりますので、言われたとおりにするべきです。
パターンの一例です
- 売買契約締結前でご主人様単独から奥様が自己資金を出すため共有名義に変更
- 売買契約締結前でご主人様単独から奥様も融資を受け連帯債務等の方法に変更するため共有名義に変更
不動産購入時の名義予定の人が【増加】した場合で不動産売買契約の後の場合

〇住宅ローンを利用するのであれば、手続きが煩雑になります。
銀行によって対応は様々だと思いますが、事前審査からやり直すのか、本審査で一気に審査をするのかも銀行の判断になります。そして、追加買主様の住民票・印鑑証明書・実印や身分証明書が必要になります。
最初に不動産売買契約書に対して追加買主を有効にする必要があり、これは、「覚書」での対応となります。売主様・買主様それぞれ覚書原本を保管してもらいます。この時に収入印紙200円を貼り忘れ無いようにご注意ください。
実務では、買主様のご都合による変更ですから、売主様分の収入印紙200円を買主様が負担することが多かったです。
【住宅ローン利用の場合】不動産購入時の名義予定の人が【減少】した場合で売買契約前の場合・売買契約後の場合
遠慮なく不動産業者に相談してください。そして、相談する時は出来るだけ早めにしてください。
不動産業者が火曜日や水曜日の休みでも時と場合によっては遠慮なく電話した方が良いです。正直な話、その方がかえって良かったりもするものです。
不動産購入時の名義予定の人が【減少】した場合で不動産売買契約の前の場合

〇住宅ローンを利用するのであれば、少し手続きが煩雑になります。
銀行によって対応は様々だと思いますが、売買契約前ですが、住宅ローンの事前審査を行っているので、住宅ローンを利用する銀行へ名義人が減少する旨の連絡を入れ銀行の承認を受ける必要があります。
そして、銀行がそのまま売買契約書に単独買主の署名(記名)・押印をして、本申込で対応すると言えばその通りにすることで大丈夫です。
しかし、銀行が単独の状態で事前審査をやり直すとの事になったら、再事前審査を受ける事になります。
当初の共有者がいなくなった状態でも単独で住宅ローンの事前審査が通るようであれば、問題ございませんが、危ない時は行わない方が良いです。
この判断は銀行の判断になりますので、言われたとおりにするべきです。
不動産購入時の名義予定の人が【減少】した場合で不動産売買契約の後の場合

〇住宅ローンを利用するのであれば、手続きが煩雑になります。
銀行によって対応は様々だと思いますが、事前審査からやり直すのか、本審査で一気に審査をするのかも銀行の判断になります。
最初に不動産売買契約書に対して共有の買主を削除する必要があり、これは、「覚書」での対応となります。売主様・買主様それぞれ覚書原本を保管してもらいます。この時に収入印紙200円を貼り忘れ無いようにご注意ください。
実務では、買主様のご都合による変更ですから、売主様分の収入印紙200円を買主様が負担することが多かったです。
銀行によっては名義人が減る場合は承認しない場合もあります

〇銀行によっては名義人が増える場合は問題ないですが、逆に名義人が減る場合は承認しない場合もありますので、事前に住宅ローンを利用する銀行に確認が必要になります。
これは、共有者と言う担保を外してくれと言っているようなものです。銀行としても担保を外すことはリスクにつながりますので、承認しないこともあります。
ご主人様の意向で奥様にも持ち分を付けたい場合

よく言われることに、お金を出したり住宅ローンを組むのはご主人様お一人なんですが、妻にも半分の持ち分を持たせたい。
ご主人様にしてみれば、一緒に暮らしている奥様と共同で名義を付けて生活をしていきたいと思う気持ちも分かります。
しかし、全てのお金をご主人様がご準備されているのに、何のお金も出されない奥様に名義を付けることは物理的には可能ですが、やめられた方が良いと思います。
贈与に該当し贈与税が課税される可能性

理由は、奥様に贈与税がかかる可能性が高い確率であるからです。
税務署を甘く見てはいけません。この場合、ご主人様が住宅ローンをご利用されるのであれば、初年度は住宅ローン控除のための確定申告が必要です。
その際にいくらで物件を購入したか、資金調達はどうなっているのか等税務署は調べます。調べたらすぐにわかってしまいますから贈与税がかかってくることになります。
不動産の名義と言うものは単純で奥が深いものです。最初にお金の話は後回しにしないで、誰がいくら出すのかちゃんと話し合っておきましょう。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
これは本当にありがたい話しですね。どれだけ愛されているのか実感できる瞬間です。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
出典:国税庁ホームページ
気になるのはいくらまでならこの制度の非課税になるのってことでしょう。
2023年3月現在では、最高額は10,000,000になります。省エネ等住宅に当てはまらない場合は、5,000,000になります。
非課税限度額
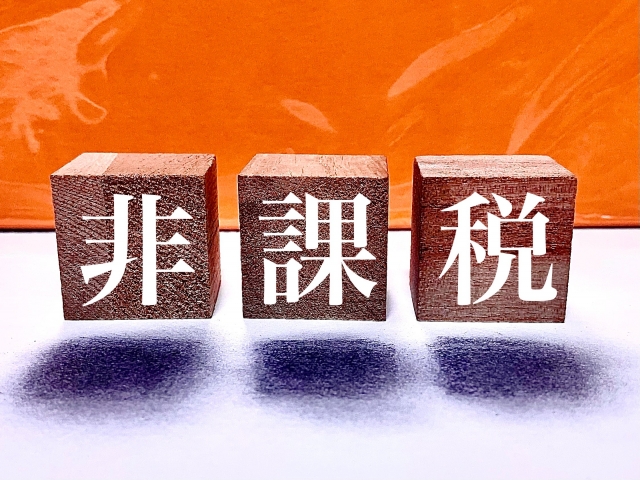
非課税限度額
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
出典:国税庁ホームページ
受贈者の要件

次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳(注)以上であること。
(注) 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」および「非居住贈与者」については、コード4432「受贈者が外国に居住しているとき」をご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、コード8007「災害を受けたときの贈与税の取扱い」をご覧ください。
出典:国税庁ホームページ
住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、その住宅の取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
(1) 新築または取得の場合の要件
イ 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④ 上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
出典:国税庁ホームページ
ここに当てはまる人ならば親御さんや祖父母に一度ご相談いただくのも手じゃないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
不動産探しから売買契約までは、購入を決めた不動産があった場合、購入申し込みから不動産売買契約までは原則1週間以内に行います。
それまでに購入資金について十分話し合いを行っておく必要があります。
また、家を買うことを親に報告すると、親や祖父祖母から資金援助の話しが急に出てくることがあります。
そうなると名義をどうするかが問題になってきます。
この記事をご覧いただき、スムーズな取引が出来ればいいと考えています。




ゼータエステートはクレジットカードで仲介手数料が支払い可能